ー カントにおける想像力とイメージ ー
1.序:カントの想像力とイメージ
想像力は像(イメージ)をこころに思い描くことと捉えられることが多い。前回、このような一般的な立場から想像力やイメージを捉え、例えば、イメージの動性がどのようにして生まれるかなどについて検討した。
本稿では、カントは想像力についてどう考えていたのか、イメージに対する見方と合わせ考察する。
純粋理性批判は有名であっても、そこで何が問題になっているのか、例えばアプリオリな総合判断とか理性の誤謬といった用語を聞いても中身はほとんど分からないのが普通だろう。何か縁があった人でも、大抵はホコリにまみれて本棚の奥で寝ているのではないか。近寄りがたさの原因は、複雑な論理構成があるにしても、むしろカント固有の緻密な概念群を表現する用語にあるように感じているのは筆者だけではなさそうだ。簡単に言えば、固有の意味を担った数多くの言葉(造語)を理解することが大変で、根気がいる。挫折する大きな理由はそこにあり、その点で数学と似ていると言えるかも知れない。
ところで、イメージやそこに関わる想像力の問題は、認識や思考にまたがる広い領域に及ぶと思われるが、カントに限らず理論的な整備が進んでいるようには見えない。
実際、カントの理論(認識論)が応用されたという議論はほとんど知られていないのではないか。カントの用語の壁は厚いこともあり、一筋縄にはいかなそうだが、応用への道がないとはだれも示したわけではない。
カントの“もの自体”は、経験する主体と独立に、それ自身として個油のあり様をしめしていると考えられる。それを不可知なものとするカントは、知り得ない“もの自体”と区別された、人間にとって感覚出来る“現象”が認識、経験の対象になるとした。
ところで、カントは“イメージ”と言う言葉自体は使っていない。ここでは試みとして、“現象”に注目し、形をもった現象をイメージと見做し、その上でカントの想像力、つまり構想力を考えていく。そうすることによって、先ずはカントの認識論の広がり、特に広範なアートなどの分野への広がりを検討したいからである。
イメージ=形をもった現象と見做すということは、言い換えれば、現象に形(形式)が与えられたものをイメージと考えることを意味する。
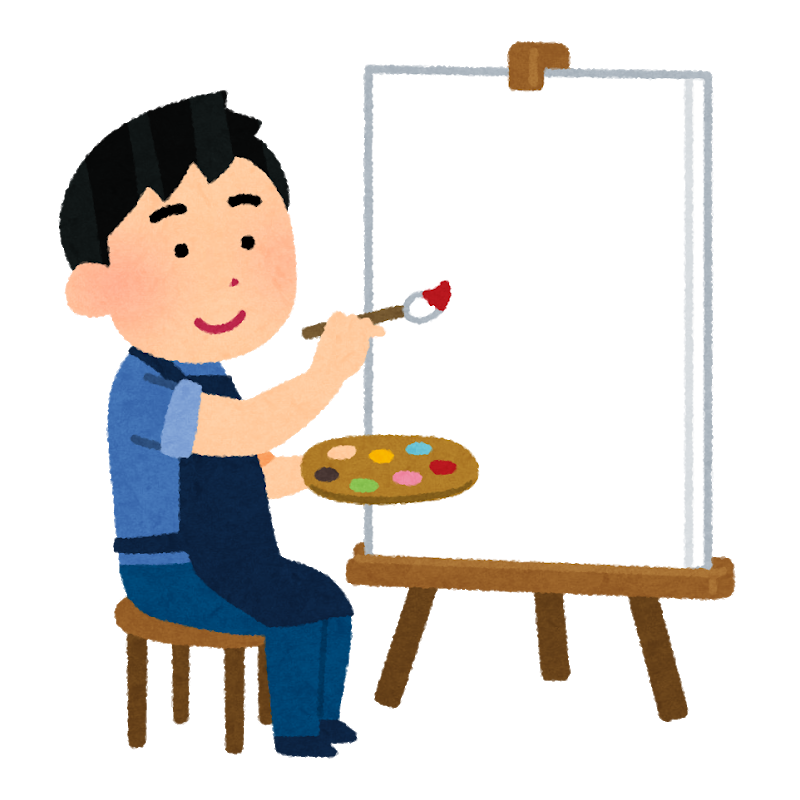
2.悟性
ところで、カントは純粋理性批において、人間の認識能力の要素として、感性、悟性、理性に着目している。(感性、悟性、理性と言う言葉は今日日常的に使われているけれど、その意味は、カントが意図した意味とは同じでないことに留意したい。)
このうち、本稿が主として関わるのは、感性と悟性である。既に説明したように、感性とは対象によって触発され、感覚的な直観として生じる多様な表象を受動的に受け入れる能力である。
悟性については、純粋理性批判でカントはいろいろな言い方をしていて、統一されていないが、緒言の中で、広い視点から次のように述べている;
「人間の認識には二つの根幹がある。恐らくこれらの根幹は、(中略)唯一の 根から生じたものであろう。この根幹というのは、即ち感性と悟性である。そして、感性によって我々に対象が与えられ、また悟性によってこの対象が考えられる(思惟される)。」
これは、人間の認識に関する感性と悟性の基本的関係を簡潔に規定しているのだが、悟性自体については、明らかに物足りない。より踏み込んだ説明が必要である。簡単に言えば、受動的な感性に対し、カントが考える能動性の能力としての悟性は、
感性が受け入れた多様な直観(印象)を総合して(まとめて)、対象についての判断をもたらす自発的能力と言えよう。言い換えると、
悟性は、感性が受け入れる質料(素材)に、形(形式)を与え、(対象について)規則づける能力、つまり、概念の能力である。
緒言での説明に似ているが、悟性についてカント自身の言葉を引いておこう。
「認識には、二つの要素が必要なのである。第一は(純粋悟性)概念(カテゴリー)であり、これによって一般に対象が思惟される。第二は直観であり、これによって、対象が与えられる。
もし概念に、これに対応する直観が与えられえないとしたら、その概念は、形式から言えば一個の思考形式であるが、対象を持たないのだから、そうした概念によってはおよそものの認識は不可能であろう。このような場合には、私の思考が適用され得る何ものもー私に知られるものとしてはー全く存在しないし、また存在しえないからである。」
上の“純粋悟性概念”という語は、
カントが、悟性の基本的特徴として、純粋悟性概念と言うアプリオリな形式の枠組みを要請したものである。つまり、(悟性の)判断には決められた形式としてカテゴリーがあり、判断はその中で行われるのである。このカテゴリーを与えるのが純粋悟性概念である。純粋悟性概念は純粋概念であって、数学においてその典型例が見られるような、経験には関わらない概念であり、経験的概念と区別される。

カントは判断表から、4つのカテゴリー(分量、性質、関係、様態)のそれぞれが3つの分枝を持つ計12個のカテゴリーを導き、悟性による判断の枠組みとして純粋悟性概念を与えた。またそれが、アプリオリな概念、つまり、経験に先立つ概念であることを示している。しかし、その内容の詳細にはここでは立ち入らないで、むしろ、感性によって与えられる直観的印象と悟性の思惟という全く異なった能力が何故繋がるか、という問題に注目しよう。
ここでカントが考えるのが、感性と悟性を媒介する能力としての“構想力”である。
3. 構想力と図式
もう一度繰り返しておこう:
悟性は、感性で与えられる多様な印象を結合し、形をもったモノにまとめる(総合する)という働きをする。ここで、与えられた多様を、結合し、一定の形をもったもの(姿)にまとめる(総合する)という働きは構想力によるものと考えられる。その働きは、感性と悟性双方にまたがることによって両者を媒介するのである。
ところで、想像力は一般にそこにないものを心に描く能力を言い、例えば「それは全く想像力に欠ける話だ」といったように使われる。カントの構想力は、広い意味の想像力であっても、一般的な想像力や連想とは区別され、特に“産出的な”構想力(Productive Einbildung Kraft)と呼ばれる。“産出的構想力”については後で詳しく述べるが、カントはそれと連想を特徴づける“再生的構想力”と対比して違いを強調している。
カントの構想力(産出的構想力)が一般の想像力と区別される大きな特徴は、構想力が“図式(Schema)”と呼ばれるアプリオリな形式によって支えられているからと言えるだろう。どういうことか。以下、カントの産出的構想力と図式の関係に焦点を絞って考えよう。その結果、カントが“産出的”と呼ぶ意味が明らかになるだろう。
まず、構想力や図式について、カントの言葉を聞こう:
「ある対象を一つの概念のもとに包摂する場合には、その対象はいつでも概念と同種なものでなければならない。換言すれば、その概念は、その概念のもとに包摂せられる対象において表象されるところのものを、自らのうちに含んでいなければならない。(中略1)ところで、純粋悟性概念と経験的(つまりは感性的な)直観を比較してみると、両者は異種的で、純粋悟性概念はいかなる直観においても決して見出し得ない。ならば、直観を純粋悟性概念のもとに包摂することはどうして可能か、従ってまたカテゴリーを現象に適応することはどうして可能だろうか。(中略2)すると、一方でカテゴリーと、また他方では現象とそれぞれ同種的であって、しかもカテゴリーを現象に適用することを可能にするような第三のものがなければならないことは明らかである。このような媒介的な役目をする表象は、(経験的なものを一切含まない)純粋な表象であって、しかも一方では知性的で、また他方では感性的なものでなければならない。このような表象が超越論的(transzendentales Schema)なのである。」
上の文では、構想力がなぜ問題になるのか、カント自身の問題意識や基本的な考え方(哲学的な立場)が踏み込んで述べられている
以下、それを少し読み解くことにしよう。まず、前半でカントが考える問題点が指摘される。つまり、悟性の基礎にある純粋悟性概念は経験と無関係なものであるのに対して、感性による経験的直観は必ず感覚を介して経験される。だから、両者は全く別のものである。にも拘らず、私たちは、現象を直観して、それが何であるかを判断し、認識するという経験をしている。と言うことは、こういった両者に関して、後者=経験的直観を前者=純粋悟性概念に包摂する、つまり直観を概念の中に包み込むこと、また逆に、カテゴリー(=純粋悟性概念)を与えられた現象(=感覚的に直観されたこと)に適用しているが、これらをどう考えれば良いのか? 以上が前半部分である。
更に問題を明確に指摘しているのが、後半である。つまり、カテゴリーを現象へ適用するためには、一方でカテゴリーと、他方では現象と同じ種類になる必要があるが、そのためには両者を媒介する第三のモノが必要であろう。
それを(構想力として)可能にするのが“超越論的図式”である。
この説明にある、図式とは何なのか? 図式はSchemaの訳語であり、図式には、図取り、つまり物の形を図として描くこと、あるいは、基本的な見取り図と言う意味がある。しかしここでは、図式の日本語の意味にはないが、その原語Schemaがもつ意味、即ち、計画(する)あるいは、あまり良い意味には使われないが、たくらみ(たくらむ)という意味がより近いと思われる。何故なら、その場合、“超越論的“な図式とは、構想力を可能にしている無意識のうちで支える計画、言い換えれば、構想力を可能にしている意識下ではたらく構えという解釈に素直に導くことになるからである。なお、ここで超越論的とは、簡単には、経験より前に(アプリオリに)、いわば本能的に決まっているという意味と考えられる。
ついでながら、図式ということばを一般に広めた、メルロポンティの身体図式の図式も、その意味を計画として、無意識のうちの身体計画と解釈すれば、メルロポンティとカントの繫がりをより鮮明にするのに役立つかも知れない。ここには、広い意味で感性の問題と思われている、合気道など身体性に関わる面白い問題があるように思われる。
ここで、カントが構想力とした生成的構成力とは何かということも取り上げておこう。上で見たように、図式に従って構成力を働かせる時、(1)現象には、素材に形が与えられる、あるいは、(2)概念に直観が与えられる。つまり、構成力が働くとき、そこには、形をもった現象(=イメージ)が無意識のうちに生成されている。このことは、カントが“生成的“構想力と呼ぶことと呼応している。また、このようなアプリオリで非経験的な構想力と、経験的な構想力との違いは明らかだろう。
悟性による判断の特徴は、閉じていた目を開けた時、目を開けた途端直ちに外部にある対象の姿が現れ、それが何であるかを直ちに知ることができるというところに見られる。つまり、アプリオリな純粋悟性概念がアプリオリに(=経験に先立って)働いているという性質にある。
4.まとめ
カントの悟性を知性と解釈することがある。その意味での知性かどうかは不明だが、一般に、知性は感性とは全く別の、互いにつながりのない存在と見做されているよう思われる。
こうした見方は一種の常識のようだが、本稿での議論から明らかなように、カントの感性と悟性は、互いに連携して初めて物事の認識が可能にしている。逆に言えば、感性も悟性も単独では何の機能も持ち得ないということである。
また、カントの哲学はしばしば“意識の哲学”と呼ばれる。これは、デカルトの言明「我考える、故に我あり」によって、意識が哲学の主要なターゲットとして浮かび上がった歴史的経緯において、カントがその延長上に位置づけられていることを意味している。ところが、カントの認識論の基本には、決して意識にのぼる事柄のみで成立するものではなく、むしろ意識下にあって、意識されずに働いてしまう思惟の働きの中にこそ、人間の認識の枠が決まっているという思想がある。
その意味で超越論的図式論は重要で、カントが想像力として考えた構想力=産出的想像力は、構想力のアプリオリな枠組みを与える超越論的図式によって意味が定まる。
本稿を終える前に、前回までに議論された、創造性に関する問題に触れておこう。
問題の一つは、貧しい感性と見る立場から、カントの感性に創造性があるか、否かという事であった。筆者の考えでは、貧しい感性が創造性を持つという主張は、本稿で立ち入って議論したように、感性と言う言葉の使い方に問題があり、厳密言うと「貧しい感性に創造性はない」と言わざるを得ない。むしろ、問題は感性でなく、むしろ創造性は構想力の領域に関係を持ち、その中で検討すべき課題ではなかろうか。
カントは美的感受性やまた天才について、純粋理性批判とは別のところで論じているが、創造性をストレートに取り上げてはいないようだ。ストレートに言ってはいないが、本稿の図式論における“現象に形を与える“といった見方などは、創造性に必須な要件だろう。
なお、本稿の冒頭などで、カントの認識論のアートへの応用などと言ったことに、読者の中には真意を測りかね、筆者が全く誤解しているのではないかと感じている人もいるかも知れない。その問題については、本稿は必要な議論を全く欠いている。それらに関しては、いずれ本稿の展開を試みたい。
長島 知正 2020-09-28
付記:本稿で引いたカントの純粋理性批判は岩波文庫(篠田英雄訳)である。ただし、”先験的”を”超越論的”に変えるなど、今日標準と見做されている文言の修正を加えた。