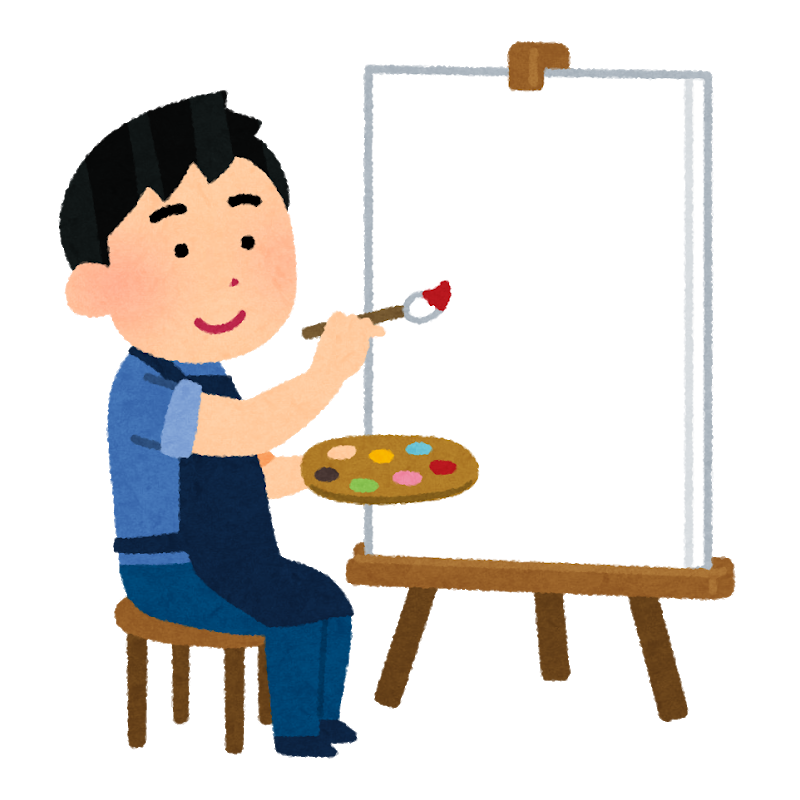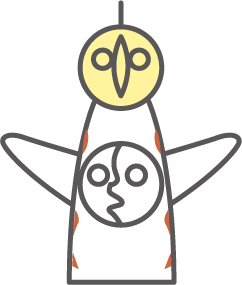― リアリティの謎 ―
イメージとは
イメージという言葉が使われる範囲はきわめて広い。というより、範囲を限定する方が難しいかも知れない。使われ方を少し考えてみよう。例えば、「その話は私のイメージに合わない」のように使われるが、これは、その話は私の考え方とは違う、という事を意味する一方、その話の内容は私の好み(趣味)が違う、ということにもなり得る。上の例からイメージは、考え方や好み(趣味)を表していて、思考から気持ち、感情に及んでいる。 また、「それは、イタリアのイメージだ」という場合、イメージは印象、観念を表している。
上の僅かな例ですら、イメージの意味するモノは極めて広がっていて、そうした全体をまとめて把握することを難しくしている。ここでは、イメージとは、像、つまり、形をもった現象として私たちに感覚的に見える(捉えられる)もの、言い換えれば感覚的に意識にあらわれるものとして議論を進めたい。
とは言え、このように限定しても、従来からイメージの典型的な対象とされた絵画などの芸術作品はもちろん、写真や映像のような像はもとより、私たちの普通の生活で目に映る物体の知覚像、過去の記憶、夢なども含まれることに注意しておきたい。
本稿は、こうしたイメージを念頭におくけれど、焦点を当てることはイメージ自身でなく、”イメージともの”との関係を手掛かりに、イメージのリアリティについて考察したい。
普通、リアリティあるいはリアルさは、現実が示す生々しいあり様、言い換えれば、我々が実際に日常経験している世界を基準にした “現実性 ”、“実在性“を言う。その意味で、絵画や小説のような創作作品にリアリティはない。それ故、それらは、現実から離れた”虚構“と呼ばれる。だが、それは何処かオカシクないか。確かにどんな写実絵であっても、実在しない世界のものだが、絵画などの芸術作品に我々は、ハッとするような 何らかの“リアルさ“を覚えるからだ。
我々の経験はリアリティによって支えられ、それが日常を成り立たせているけれど、果たしてリアリティとは現実世界を基準にした実在性のみで捉えられるものだろうか。
2.5次元文化
最近の話題になっている一つに2.5次元文化と呼ばれるものがある。2.5次元と言う言葉の由来は、アニメや漫画の中の2次元キャラクタを、現実の3次元の舞台において、俳優が観客の前で演じる事にあるようだ。例えば、アイドルグループをテーマにしたアニメのキャラクタ役の声優たちが、紅白(NHK)の舞台等に出演したり、また多くの女性ファンに支持されている漫画をミュージカルにした舞台が評判を呼び、長期間公演されている。
漫画やアニメのキャラクタが話題になること自体は別に新しいことでない。漫画が週刊誌化されてから半世紀ほどになるが、その当時通勤途中のサラリーマンは新刊が発行されると、赤塚不二夫などの作家が描く個性あふれるキャラクタマンガを買い求め、むさぶるように読んでいたし、その一方で、ミッキーマウスなどのディズニー映画のキャラクタは独特のファンタジーの世界に欠かせない存在となっていた。
漫画やアニメは今や単なるブームを超えるほど盛況だが、現在、さらに2.5次元文化と呼ばれる新たな事態が起きてきた大きな背景に、IT・インターネットの急激な普及、とりわけ ”仮想現実感(Virtual Reality)” の影響があるようだ。
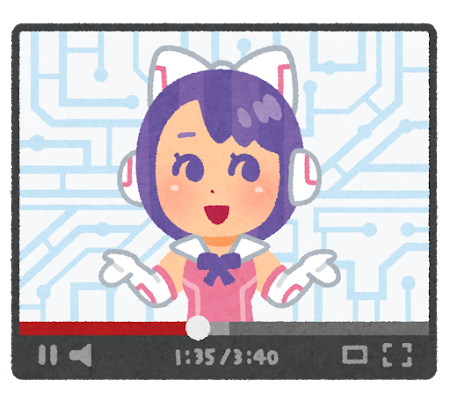
その意味で、最近バーチャル・ユーチューバーなどで話題になるバーチャル・アイドルの先駆けとして、ここでは2007年札幌のベンチャー企業が発売した音声合成ソフト、ボーカロイドのキャラクタ:初音ミクに触れておこう。音声合成といっても、初音ミクは歌詞とメロディーを与えると歌い上げるソフトで、著者がその歌声をはじめて聴いた時、コンピュータによる合成という先入観を疑うほど滑らかで、印象に残った。
実際、自作した曲を初音ミクに歌わせて動画サイトに投稿する人が一気に増え、気に入った歌に動画をつけて再投稿する創作の連鎖現象も起きた。当初ネットのなかの歌姫であったミクはしばらくするとネットから出るようになったが、武道館でのイベントで生バンドと共演し、歌声と共にCGによって透過型スクリーン投影されて踊る”彼女”は歌手が実際に歌っているとしか思えない臨場感で大きな話題をさらった。
その後、しばらく初音ミクの話題から遠ざかり、忘れかけていたが、偶然、初音ミクと結婚式を挙げ、友人を招き本格的披露宴を行ったという男性が現れたという“事件“を新聞で知った。ミクのぬいぐるみの指に結婚リングをはめ、簡単な会話を交わしているというその男性Kさんは、初音ミクは何よりも大切な存在と言いきっている。Kさんは変人なのか。どうもそうとは言えないらしい。ある企業がバーチャル・アイドルと婚姻するという企画をしたところ、わずかな期間に数千通の婚姻届けが集まったと言うからだ。これは、アイドルに対するファン心理に過ぎないのだろうか。
ニコニコ動画がネット文化の黎明期を牽引したことは良く知られているが、近年その利用者は急減していると言う。人気を集めているのは、ネットから現実社会に飛び出した文化祭のようなイベントらしい。こうした中で、リアルと仮想(非リアル)が混在する2.5次元の事業が注目され、市場規模を拡大していると言われる。
2.5次元文化の人気の秘密は、研究者によると、2.5次元の文化では、漫画やアニメの2次元キャラクタの挙動を現実の3次元の空間に再現された人間の演技を見て、聞くことで、多くの観客と同一の空間を共有することにより一層深い没入感を得て、(元々のアニメや漫画とは異なった)新たな体験がもたらされるのだと言われている。
元々の漫画やアニメの(2次元の)キャラクタに共感することとは昔からあったが、2.5次元文化の現象の本質とはどう違うのだろう。
リアリティとは何か
リアリティは、元来、想像ではなく現に存在する、実在のあり様を表すとされる。特にものの実在については、古くから哲学で議論がなされてきたが、最近は、コンピュータによるネット世界を非実在全般と同一視して議論する傾向が生まれてきたようだ。しかし、それはコンピュータによる仮想的世界以外に、人間が普通に使う言葉に見られる非実在の世界があることを見落とした短絡的な見方ではないだろうか。むしろ、コンピュータによる仮想的世界と、人間の言葉にみられるような非実在的なものとを切り離してしまうのではなく、相互の繫がりの中に今後の人工知能などIT技術の重要なヒントがあるのではないか。
以下では、実在するとふつう思われているモノと非実在のイメージを取り上げ、それらの”リアリティ”を考察する。
序章で触れたように、イメージは我々の経験のほとんど全てに関わりを持っているが、日常生活において、イメージを正面から意識する機会すくない。結果、日常的にイメージの作用としてのリアリティを感じることは余りない。何故こうなるのか。

この事態には、日常生活におけるイメージの特殊な在り方が関係していそうだ。
まず、今日イメージはより強力な存在であることばの影響から逃れられない、と言う事が挙げられる。
つまり、イメージは生まれながらにして言葉と切り離せない関係にある。それは、生まれ落ちた人間が言葉を覚えていく時のことを考えれば良い。例えば、イヌという言葉を覚える時、「あれがイヌよ」とやることから始まる。即ち、私たちは生まれたときから、イメージを言葉に結び付けている訳だが、つまるところ、イメージはことばに置き換えるよう教えられるのである。
人はこのやり方を様々なものに適用し、何度も繰り返すことによって、言葉(母国語)を獲得する。
この過程で、様々なイメージは各々の名前(言葉)に換えられ、イメージにたよっていたことはすっかり忘れ、より安定したことばだけで様々なことに対処するようになる。こうして、日常生活において、直接的なイメージの力、リアリティの経験は遠ざけられる。
更に、ことばはイメージよりものと結びついて威力を発揮してきた。つまり、ことばが指示する先にはモノがある(存在する)という強い信念がある。端的に言うと、言葉が指示するのはイメージでなくモノである、ということだ。
この信念は、科学のみならず、広く常識の中に浸され、容易に崩れることはない。
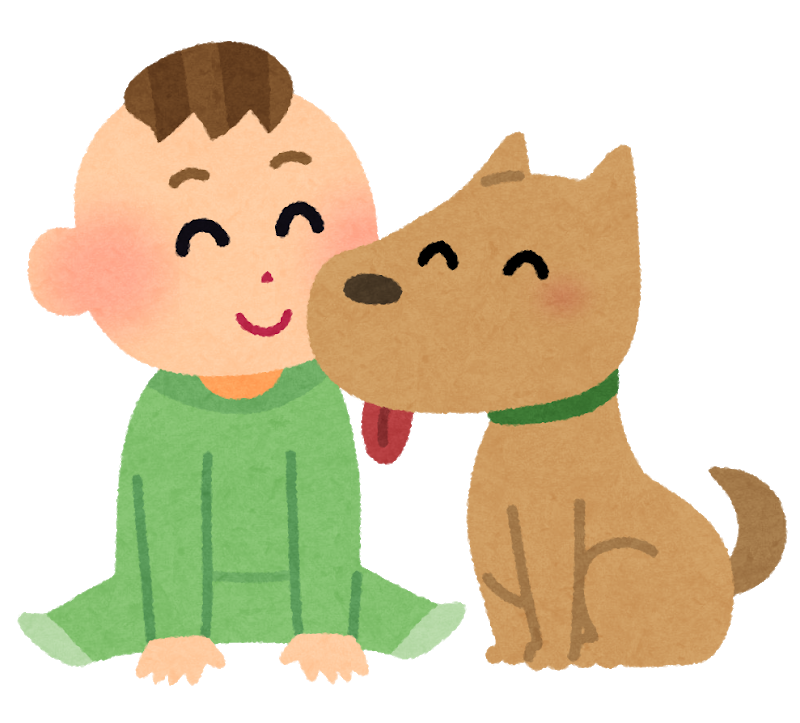
素朴実在論はこの常識と整合性を保ち、すっかり安定しているように見えるが、果たして、モノは確実に存在していると言えるのだろうか。モノの存在は、古来議論されてきたが、ここでは、存在すると思われているモノそれ自体ではなく、私たちが見たり、触れて経験できる、感覚的に捉えられる範囲の存在を対象として考察する。
我々が経験できる”形を持った現象 ”はイメージだが、それは、普通信じられているようなモノの実在(リアリティ)とは異なるリアリティ(実在性)をもつと考えられる。
例えば、暗い夜道でとぐろをまいて横たわるモノに出会った時、瞬間的にヘビだと身構えたが、翌日明るい中で見ると、それはゴム紐だったと言う経験は良く聞く。これは普通、ゴム紐をヘビと取り違えた錯覚、つまり、ヘビは誤りで、正しいのはゴム紐だ、と言われる。しかし、この常識的な結論は事後的な思考から導かれたもので、夫々の経験の現場では、ヘビであり、またゴム紐であることはどちらもまぎれもなくリアルなものだった。
上のヘビは間違いで正しいのは紐だという結論は事後的に、それも全く異なった状況で起きた出来事を比較することで導かれていて、比較しない時、どちらが正しいと言えると思うことが錯誤ではないか。
議論をまとめると、たとえ間違いであったこと後で分かったとしても、私たちはモノを見、触れるその場面では、対象そのものを見、触れていると考える。つまり、
それぞれの経験の現場で現象に直観的に感じたものこそ、リアルな姿(リアリティ)をあらわしていると考えられる。イメージのリアリティ(実在性)とはこういうものだろう。
まとめ:イメージのリアリティ
私たちはふつうリアリティを“実在性”、即ち現実に存在している(思っている)事物を絶対的な基準にして測る。
この基準に立てば、創作活動によるアート作品等はすべて虚構だから、そうした世界にはなんの実在性をもたない。
このリアリティを巡る謎は、リアリティ(実在性)の基準を相対化することを迫っているように思われる。
モノが確実に存在するという信念を、私たちは常識と思っている。この信念は自然科学を支え発展させてきたとは言え、私たち自らが経験できることに基礎を置いて考えようとするなら、私たちがふつう経験しているのは、モノ自体ではなく、イメージ(形をもった現象)であることに目を向ける必要がある。
イメージは、モノの概念とは異なり、前節述べた例のように、状況によって異なるリアルさを示す。それは古くから受け入れられている現実性、実在性とは異なるリアルさを捉えている。
このリアルさは私たちの直観が捉える感性から生じるもので、どんなリアリティも感性なしに生まれることはない。
なお、前節のべた、暗い夜道で見たゴム紐と明るい日差しの下で見るヘビは、対象が全く異なる状況に置かれたイメージの例であったが、それは芸術作品の世界(虚構)を現実世界と比較して、芸術作品の世界を虚構と見做す議論にも通底する面がある。結果、芸術作品と現実世界(の現象)は、イメージを媒介にして、相対的に異なったそれぞれのリアリティを現すと考えられる。ただし、創作されたものは、何であってもリアリティがあると言うのでは勿論ない。創作された作品が独特のリアリティを示すには、作品イメージの要素(*補足)の間に適切な関係が求められるのは当然である。
上のリアリティをどう捉えるかは、人工現実感(VR)を初めとする21世紀のIT技術の課題であるのみならず、今後のIT技術と人との関係(付き合い方)のカギを握っているのではないだろうか。
本稿における、イメージのリアリティの捉え方の基本はカントの感性論にある。カントの感性は、ふつうの感覚以前の非常に抽象的で捉えにくいものだが、21世紀のIT時代の感性の基礎になるかも知れない。
IT技術をカントの感性によって捉える詳しい議論は今後の課題としたい。
長島 知正 2021ー05-15
(*)補足:
最後に、イメージの要素について、少しだけ補足しておこう。
イメージは観念ではなく、経験可能なものである。概念の典型は数学、例えば、幾何学の点や線に見られる。しかし、幾何学における基本的要素として点や線は決して観測できるものではない。我々は点や線を小さな丸や細い線分として表示する習慣があるが、それらは数学的な点や線を便宜的に目に見える形に表した点や線分のイメージである。つまり、我々はそうした対象を感覚的にイメージとして表現しているのだ。